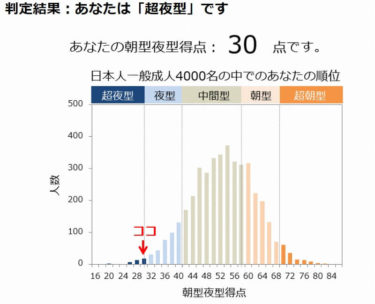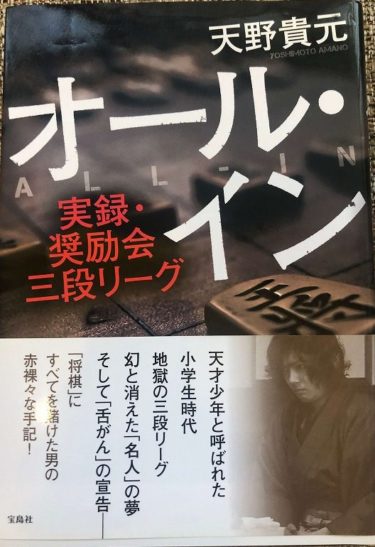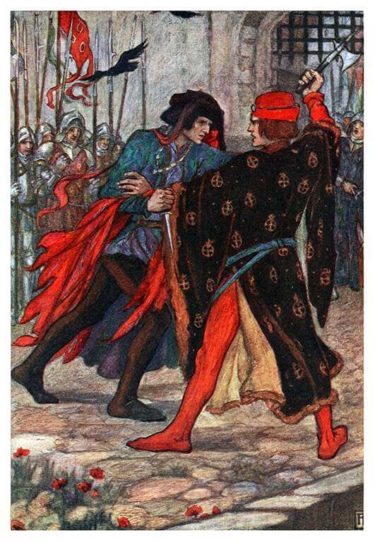少し前のニュースになりますが、エボラ出血熱に有効と思われる試験薬が見つかったそうです。
2種類の薬エボラ出血熱に効果、臨床試験で致死率約30%まで減少
臨床段階とはいえ、これを知って「医学、スゲー!」と思った人、多いでしょう。発症したら半分から9割が死亡する病でしたからね。
ただ、考えてみると致死率30%ってそれでも異様です。
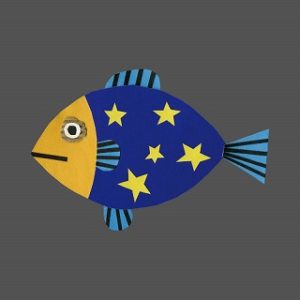
よくご存じですね。
われわれ40代以上の人間にとって「エイズといえば死そのもの!」でした。80年代後半から90年代におけるエイズの恐怖の大魔王ぶりときたら。
けれど、調べてみると当時ですら死亡率は20%前後だったらしいのです。
ひるがえってエボラの殺傷力ときや!という気がします。エボラに改めて興味が湧いた今回、エボラ出血熱がらみの本をリレー形式で読んでみました。
『エボラVS人類 終わりなき戦い』日本にエボラが来たらどうなる?
まず、1冊目。こちらはやや実用書より。2014年のエボラ出血熱大流行のさ中に(たぶん)緊急出版された本です。過去の文献などをまとめ、まざまな感染症やエボラの歴史、エボラとは何かをピンポイントでまとめた感じ。
14年のアフリカでのアウトブレイクについては時系列で出来事を追い、非常にわかりやすいです。
あの時、ヤフーニュースの前で「これはマズい、さすがにヤバい」と冷や汗かいた記憶はあるのですが、国連が「あと60日が勝負、負ければ人類は敗北」なんて悲壮な発言をしていたことは、すっかり忘れていました。
なお、感染拡大が最も深刻だったリベリアでは、内戦の影響で人口430万人中50人しか医者がいなかったのだそうです。
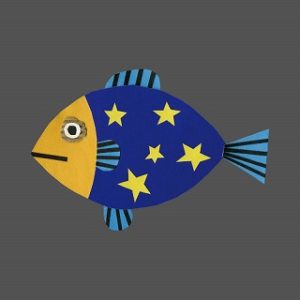
これについて持つべき言葉はありません。
言葉がないといえば、エボラ最初の感染年となった、1976年のザィールの伝道病院の話も悲惨。もう悲惨すぎます。
キリスト教のシスターが無料の処置を行っていたこの病院に、医師はいませんでした。患者の大半は地域の妊婦たちで、お目当ては打つと元気になるビタミン注射(魔法の注射とまで言われていた)。でもって、その注射、針が使い回しだった。
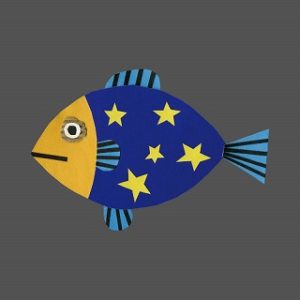
そして、ある時、エボラ患者がやってきた。シスターはマラリアと思い、注射を打った。そうして、その注射針を使って妊婦にビタミン注射を打った……。
妊婦さんが感染し、その家族が感染し、手当てをしていたシスターも感染し、多数の死者が出たそうです。無料の伝道病院です。この神のいない感じには呆然としてしまう。
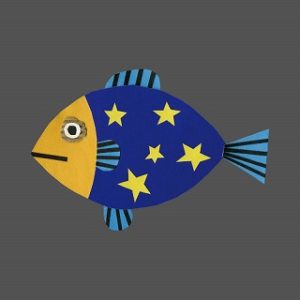
そのシュミレーションもしっかりとあります。
結論からいうと、日本の場合、そこまで世紀末的な様相にはならないのではないか、とのこと。大事なポイントは2つ。
インフルエンザのようなパンデミックは逆に起こりにくいウィルスなのではないかと著者は言います。ただ、駅のトイレはできるだけ使わない方がいいですよ、と。
駅員さんや清掃業者の方はどうしたらいいのだ、と思ってしまいましたが。
『ホットゾーン』世界でもっとも読まれたエボラ本は徹夜覚悟で!
2冊目。エボラといえば『ホットゾーン』です。
エボラ出血熱の本で世界で一番読まれ、おそらく一番面白い本。
ここでいう「面白さ」とは不謹慎ながら「一気読みミステリー」のような「面白さ」です。作者のリチャード・プレストンはマイケル・クライトン(『ジュラシックパーク』などの作者)の未完の遺稿を完成させたほどですから、ストーリーテラーの才は十分に。
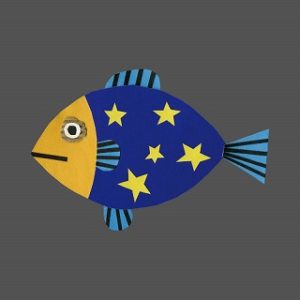
実話です。アフリカやアメリカで実際に起こったエボラパニックを描いたものです。それゆえ専門家からは賛否両論だったわけです。たとえば、次のような描写が出てくる。グロいですから、苦手な方はスクロールしましょう。
「彼はがくっと前にのめり、膝に顔をのせると同時に、信じられないほど大量の血を胃から吐き出して、苦しげな呻き声と共に床にまき散らす。(中略)次いで、シーツを真っ二つに引き裂いたような音がする。それは肛門の括約筋がひらいて、大量の血を排出した音だ。」
専門家によると、こうした描写のせいで「エボラ=血を流しながら人体が崩壊する病気」といったイメージが広がってしまった、と。いたずらに恐怖心をあおるとはまことにけしからん、ということらしく。
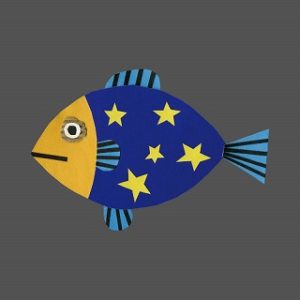
そうとも言えません。
別の本によると、エボラの初期はインフルエンザによく似ており、患者全員が出血するわけではないという。
「出血するのは全患者の70%程度」、またまた別の本によると「患者の半数程度」。十分多いじゃんかという気もしますがね。
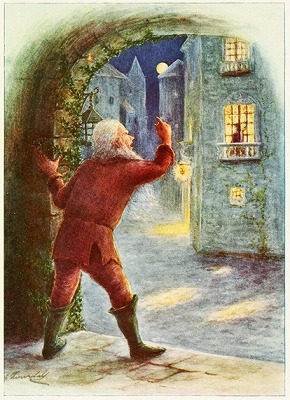
さて、本書の舞台は1967年から1993年までです。
「最初の患者や医療従事者の感染」「実験中に防護服が破れ、ヤバいことになった女性研究者」、「エボラパニックを封じ込めようとする軍らの戦い」等々中編小説のごとく登場人物が入れ替わり、ドラマが展開していく構成。ドラマなんて書いてはいけないのかもしれませんが。
ちなみに、「実験中に防護服が破れ、ヤバいことになった女性研究者」、実在の人物ですがちょっとイライラしますよ。
大事なエボラ実験の前日に手をケガするのです。
缶切りを探すのが面倒くさくてナイフで缶詰を空けようとし、手の甲だか平だかをズバッと切るのです。で、実験当日、今度はウィルスに触れている最中に防護服の破れに気づく。
傷口にウィルスが入り込んだらアウト!なのに。
事前チェックちゃんとせいよ!!
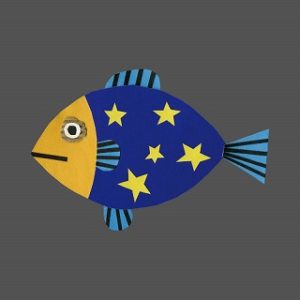
まさに。
結末は書きませんが、この人は別のエピソードにも登場します。優秀な女性研究者としてね。どこが優秀なんだ!!とツッコミを入れたくなりました。私が研究所の人間なら「エボラ」問題より、そんな人物がウィルス機関に存在することを問題視したくなりますよ。
それはともあれ、初版発行は94年。
情報は古いところもありますが、一番古さを感じたのはエボラではなくHIVについての記載でしたが。前述したように、本書が書かれた90年代初期といえば、エイズが最も恐れられていた時代ですからね。
一方、初版発行から25年近くたってもエボラについてまだまだわからないことは多い。発生源(宿主は誰か?)は何なのか、今も断言はできないのでした。
『エボラの正体 死のウィルスの謎を追う』『ホットゾーン』を1章かけて批判
3冊目。こちらも非常に読みやすいノンフィクションです。
下世話な面白ポイントを先にあげますと『ホットゾーン』を1章かけて批判していること(chapter9 正確さ描く『ホットゾーン』)。
エボラの専門家にインタビューし「壁に血しぶきなんか飛ばないし、血の涙なんか流さない。人がスライム状になったりなんかしない」と一蹴させたりね。
ただし、私が読んだ『ホットゾーン』にはここでいう描写は見当たらなかったような。
新版だったからか、日本語訳の段階で考慮されていたのでしょうか。本書によると、末期のサインは出血ではなく頻呼吸や尿が出ない、しゃっくりの症状だといいます。

わけないでしょう。
『ホットゾーン』をクサすだけではなく同書によりエボラが注目され、その後の研究資金がケタ違いに集めやすくなった事実にも触れられていますよ。
でもって、『ホットゾーン』での問い、エボラの保有宿主は誰か?をさらに掘り下げています。
エボラウィルスが動物から人間にどのように乗り移るのか、著者自らジャングルに分け入って取材した力作です。
軽くおさらいしますが、エボラは2014年に大流行したものの、それ以前は常に流行っていたわけではありません。患者数も少なく、数人から数十人規模に感染しては終息する。かと思えば忘れた頃に患者が再び現れたり。そんなことの繰り返し。
で、研究者は考えるわけです。
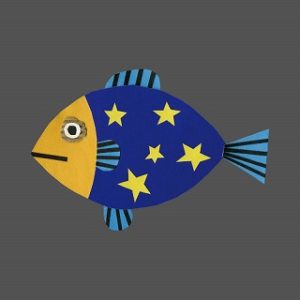
その通り。ちなみに、宿主はエボラと共存することができ、ほぼ発症することがありません。
で、結論を行ってしまえば、大本命はコウモリ犯人説です。
問いかけ自体は数十年前から行われていたことで、けれど、未だ決定的な証拠は見つかっておらず。
ちなみに、SARSの宿主もコウモリですが、そのことについてウィルス学者にも取材しています。
この学者チャーリーの話がまたよいのです。彼はコウモリのことなんて当初はまったく知らなかったと言います。知らなかったけれど、研究の必要性を強く感じ、共同執筆者をこう説き伏せたと。
共同執筆者「いいえ」
共同執筆者「ありません」
共同執筆者「どうかしてますよ! 僕たち、何も知らないじゃないですか」
共同執筆者「偏見どころか、情報だってない!」
チャーリー「いいかい。そんなことで引き下がるべきじゃない」
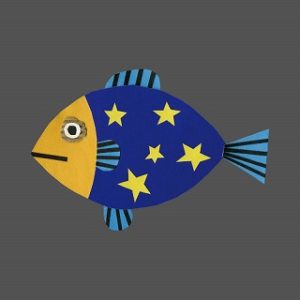
そう、引き下がるべきじゃないんです。
こういう人間が医学の進歩を支えてきたのです。
ちなみに、彼らの論文はSARSが大流行した直後に発表され、世界中の注目を集めました。
篠田節子『夏の災厄』一気読み必須!日本人にはリアルなフィクション
4冊目。篠田節子による、今度は小説になります。95年の直木賞候補にもなっていた。知らなかった。
『ホットゾーン』の半年後の出版なので作者が同書に影響を受けたかどうかはわかりません。わかりませんが、『ホットゾーン』を日本に持ち込んだみたいな設定。
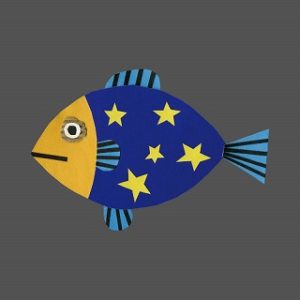
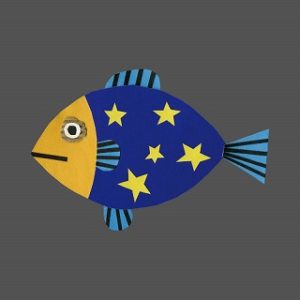
その通り。
まず楽しいイチャモンづけから始めましょうか。
本書は主要登場人物のキャラクターが時々ブレます。
「このひと、この小市民的な性格設定からすると、感染の危険を冒してまでの業務はやらんだろ!」みたいな人が何故か市民を守る行動に出たり。
遅刻魔でテキトーの代名詞みたいな男が実は英語もインドネシア語もべらべらで交渉の達人だったり。
もっと言えば、仲間が感染し、身体がねじ曲がり、脳が溶解するような悲惨な死に方を目の当たりにしているのに、周囲はさほどショックを受けている様子がないないとか。
偏屈で有名な人間がアイス買ってきてもらっただけで、初対面の相手に重要機密をべらべら喋る!とかね。
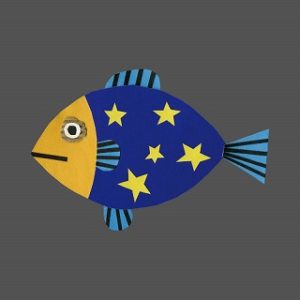
にもかかわらず。本書は正真正銘の一気読み本、徹夜本です。
そもそも一気読み本はツッコミどころがある方が楽しかったりしませんか?
「いやいや、まてまて!」と言いながらの読者参加型読書みたいな感じ。
現にイチャモンつけながらも展開にハラハラしていた自分がいたわけです。2段組で380ページもあるのに関わらず1日半で読んでしまいました。
もちろん、篠田節子です。思わず考え込んでしまうようなセリフや状況も多々。
「ハザードは起きるはずはない。(中略)しかし起きるはずのないことが起きるのだ。起きるはずがない、という傲慢極まる確信のために、過去にわしは人生でもっとも大切なものを失った」という医師の言葉は深く重い。
コロナ騒動のWHOや国の対応はまさにこれでしたしね。
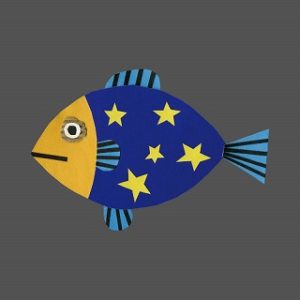
そう、製薬会社との政治的な関係とかね。市民を守るのではなく、自分たちのために守りに入る行政とか。フィクションなのに既視感ありありです。
本筋とは関係ないエピソードもまたリアルな感じ。発症した土地への偏見や差別。店は開かず、客は来ず、相次ぐ閉店。出前するのに倍の値段を取るとか。
その土地からの越境入学を反対する親が出てくるとか。やがて町はすさみ、自殺の名所になるようなマンションが出てくるとか。いかにもありえそうなストーリーが潜んでいます。
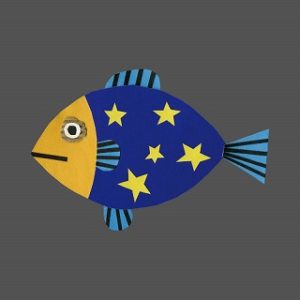
その通り。
日本を舞台にしているだけに海外のノンフィクションより、わがごととして捉えやすいです。エンタメ小説といえばその括りなのですが、パンデミックの想定準備になりえるというのか。
イチャンモンはつけたけれど、25年以上前にこんなものを書き上げた篠田節子の作家力を感じた作品でもあります。